衣帯不解とは
衣帯不解
いたい-ふかい
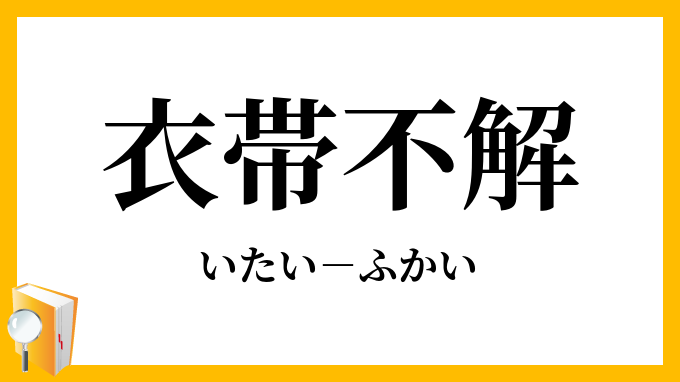
| 四字熟語 | 衣帯不解 |
|---|---|
| 読み方 | いたいふかい |
| 意味 | 他のことを忘れるほど、あることに集中すること。
「衣帯」は着物と帯のこと。 衣服も着替えず、不眠不休で仕事に取り組むことから。 「衣帯(いたい)を解かず」とも読む。 「不解衣帯」ともいう。 |
| 出典 | 『漢書』「王莽伝」 |
| 異形 | 不解衣帯(ふかいいたい) |
| 漢検級 | 5級 |
| 場面用途 | 専念する / 休まずに専念する |
| 類義語 | 昼夜兼行(ちゅうやけんこう) |
| 不眠不休(ふみんふきゅう) | |
| 一心不乱(いっしんふらん) | |
| 使用漢字 | 衣 / 帯 / 不 / 解 |



