滄海桑田とは
滄海桑田
そうかい-そうでん
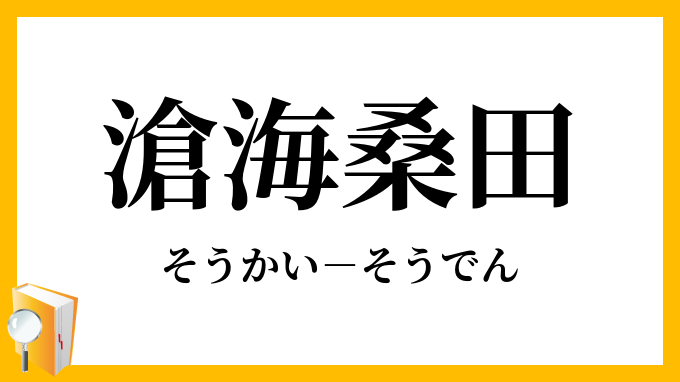
| 四字熟語 | 滄海桑田 |
|---|---|
| 読み方 | そうかいそうでん |
| 意味 | 世の中の移り変わりが激しいことのたとえ。
「滄海」は大海のこと。 「桑田」は桑畑のこと。 大海だった所が桑畑になるような変化が起こるとの意から。 「滄海変じて桑田と為る」を略した言葉。 「桑田滄海」「桑海之変」「滄桑之変」「桑田碧海」「滄桑之変」などともいう。 |
| 出典 | 『神仙伝』「麻姑」 |
| 異形 | 桑田滄海(そうでんそうかい) |
| 桑田碧海(そうでんへきかい) | |
| 滄桑之変(そうそうのへん) | |
| 桑海之変(そうかいのへん) | |
| 漢検級 | 1級 / 準1級 |
| 場面用途 | 激動 / 時世 |
| 類義語 | 滄海揚塵(そうかいようじん) |
| 陵谷遷貿(りょうこくせんぼう) | |
| 使用語彙 | 桑田 |
| 使用漢字 | 滄 / 海 / 桑 / 田 / 碧 / 之 / 変 |
「滄」を含む四字熟語
- 滄海桑田(そうかいそうでん)
- 滄海遺珠(そうかいのいしゅ)
- 滄海一粟(そうかいのいちぞく)



