郢書燕説とは
郢書燕説
えいしょ-えんせつ
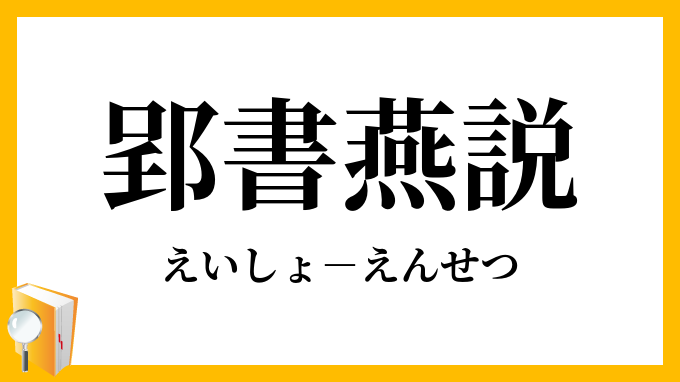
| 四字熟語 | 郢書燕説 |
|---|---|
| 読み方 | えいしょえんせつ |
| 意味 | 関連のない物事を無理に関連付けて説明すること。 「郢」は楚の国の郡の名前。 「燕」は国の名前。 郢の人が燕の大臣に手紙を書いたときに、周りが暗かったので「燭を挙げよ」と言うと、その言葉を書記がそのまま手紙に書いてしまった。 これを読んだ燕の大臣が「賢人を登用せよ」という意味だと無理矢理解釈して王に進言して実行すると国がよく治まったという故事から。 |
| 出典 | 『韓非子』「外儲説・左上」 |
| 漢検級 | 1級 |
| 場面用途 | こじつける |
| 使用漢字 | 郢 / 書 / 燕 / 説 |



