巣林一枝とは
巣林一枝
そうりん-いっし
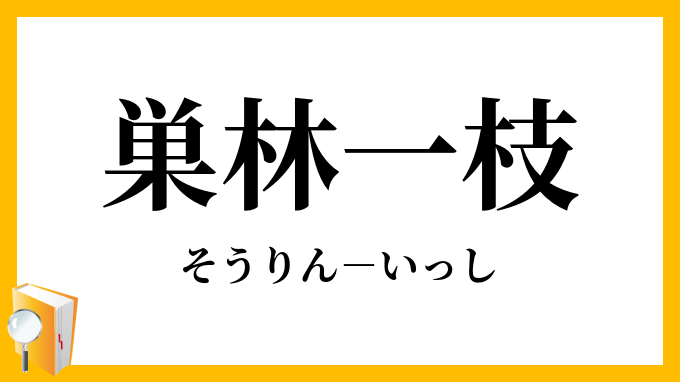
| 四字熟語 | 巣林一枝 |
|---|---|
| 読み方 | そうりんいっし |
| 意味 | 分相応の暮らしに満足すること。
「巣林」は林に巣を作ること。 「一枝」は一本の枝のこと。 鳥は林の中にある木の一本の枝だけを使って巣を作ることから。 「一枝巣林」ともいう。 |
| 出典 | 『荘子』「逍遥遊」 |
| 異形 | 一枝巣林(いっしそうりん) |
| 漢検級 | 準2級 |
| 場面用途 | 現状に満足する / 満足 / 分相応に満足する |
| 類義語 | 安分守己(あんぶんしゅき) |
| 飲河之願(いんかのねがい) | |
| 飲河満腹(いんかまんぷく) | |
| 知足安分(ちそくあんぶん) | |
| 使用漢字 | 巣 / 林 / 一 / 枝 |



