七転八起とは
七転八起
しちてん-はっき
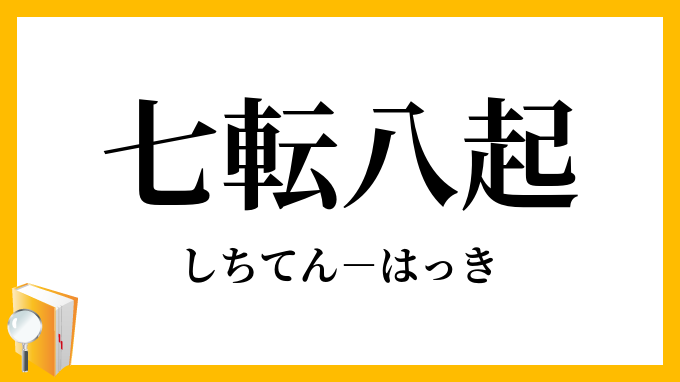
| 四字熟語 | 七転八起 |
|---|---|
| 読み方 | しちてんはっき |
| 意味 | 七回転んでも八回起き上がるという意味から、何度失敗してもくじけずに奮闘すること。
「七転び八起き(ななころびやおき)」とも読む。 |
| 漢検級 | 5級 |
| 場面用途 | 諦めない |
| 類義語 | 捲土重来(けんどちょうらい) |
| 不撓不屈(ふとうふくつ) | |
| 勇猛精進(ゆうもうしょうじん) | |
| 使用漢字 | 七 / 転 / 八 / 起 |
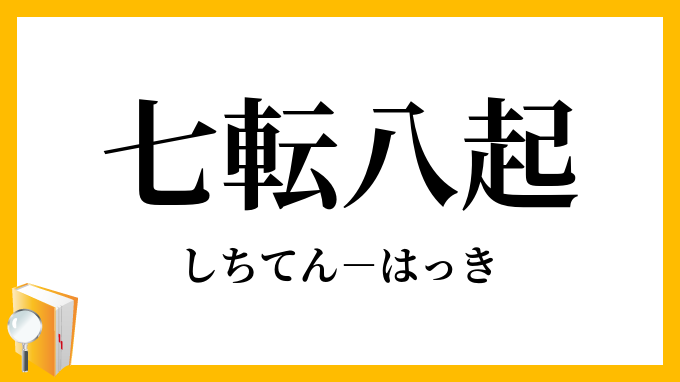
| 四字熟語 | 七転八起 |
|---|---|
| 読み方 | しちてんはっき |
| 意味 | 七回転んでも八回起き上がるという意味から、何度失敗してもくじけずに奮闘すること。
「七転び八起き(ななころびやおき)」とも読む。 |
| 漢検級 | 5級 |
| 場面用途 | 諦めない |
| 類義語 | 捲土重来(けんどちょうらい) |
| 不撓不屈(ふとうふくつ) | |
| 勇猛精進(ゆうもうしょうじん) | |
| 使用漢字 | 七 / 転 / 八 / 起 |