雷轟電撃とは
雷轟電撃
らいごう-でんげき
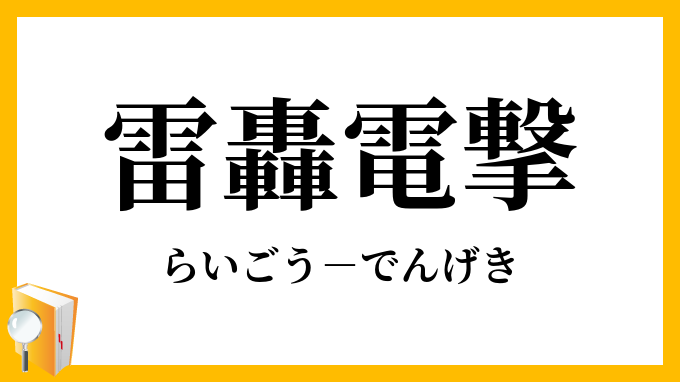
| 四字熟語 | 雷轟電撃 |
|---|---|
| 読み方 | らいごうでんげき |
| 意味 | 「雷轟」は雷が鳴り響くこと、「電撃」は稲光が走るという意味から、勢いが非常に激しいこと。 |
| 出典 | 『近古史談』「織篇」 |
| 漢検級 | 準1級 |
| 場面用途 | 盛んな勢い |
| 類義語 | 電光雷轟(でんこうらいごう) |
| 雷霆万鈞(らいていばんきん) | |
| 使用漢字 | 雷 / 轟 / 電 / 撃 |
「雷」を含む四字熟語
「轟」を含む四字熟語
- 電光雷轟(でんこうらいごう)
- 雷轟電撃(らいごうでんげき)
- 雷轟電転(らいごうでんてん)



