酒入舌出とは
酒入舌出
しゅにゅう-ぜっしゅつ
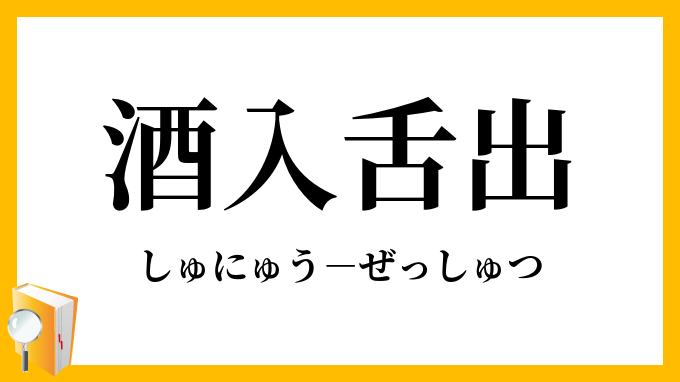
| 四字熟語 | 酒入舌出 |
|---|---|
| 読み方 | しゅにゅうぜっしゅつ |
| 意味 | 酒に酔いすぎると口数が多くなって、失言する恐れがあるということを戒めた言葉。
中国の春秋時代の斉の桓公は、大臣たちに酒を振る舞った時に、宰相の管仲は半分ほど飲んで捨てたのを見て、それを咎めると、「酒に深く酔うと失言する恐れがあり、失言して身を捨てるよりは酒を捨てるほうがよい」と答えたという故事から。 「酒(さけ)入(い)れば舌(した)出(い)ず」とも読む。 |
| 出典 | 『説苑』「敬慎」 |
| 場面用途 | 戒めの言葉 / 酒に酔う / 言葉 |
| 使用漢字 | 酒 / 入 / 舌 / 出 |



