曳尾塗中とは
曳尾塗中
えいび-とちゅう
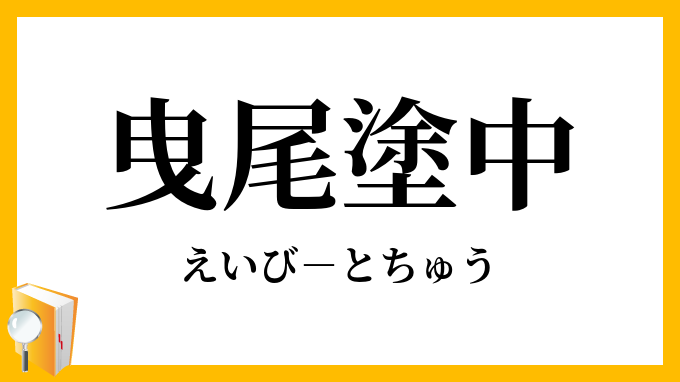
| 四字熟語 | 曳尾塗中 |
|---|---|
| 読み方 | えいびとちゅう |
| 意味 | 高い地位を得て窮屈な生活をするより、低い地位でも自由に暮らすほうがよいことのたとえ。 「塗中」は泥の中という意味。 楚王から役人に登用したいと言われた壮士が、「亀は殺されて甲羅を占いに使われて尊ばれることと、泥の中をはいずりまわって自由に生きることのどちらを選ぶか」と言い断った故事から。 |
| 出典 | 『荘子』「秋水」 |
| 使用漢字 | 曳 / 尾 / 塗 / 中 |
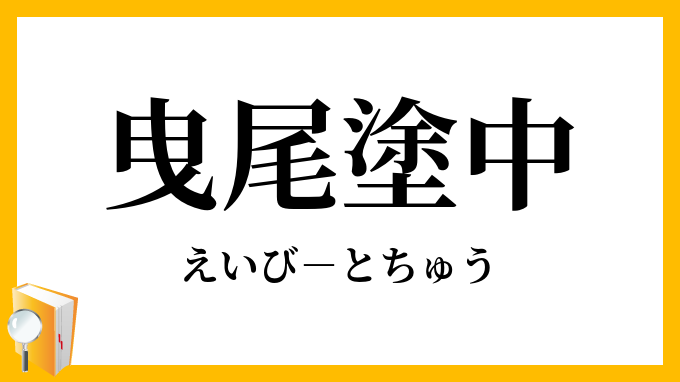
| 四字熟語 | 曳尾塗中 |
|---|---|
| 読み方 | えいびとちゅう |
| 意味 | 高い地位を得て窮屈な生活をするより、低い地位でも自由に暮らすほうがよいことのたとえ。 「塗中」は泥の中という意味。 楚王から役人に登用したいと言われた壮士が、「亀は殺されて甲羅を占いに使われて尊ばれることと、泥の中をはいずりまわって自由に生きることのどちらを選ぶか」と言い断った故事から。 |
| 出典 | 『荘子』「秋水」 |
| 使用漢字 | 曳 / 尾 / 塗 / 中 |