几案之才とは
几案之才
きあんの-さい
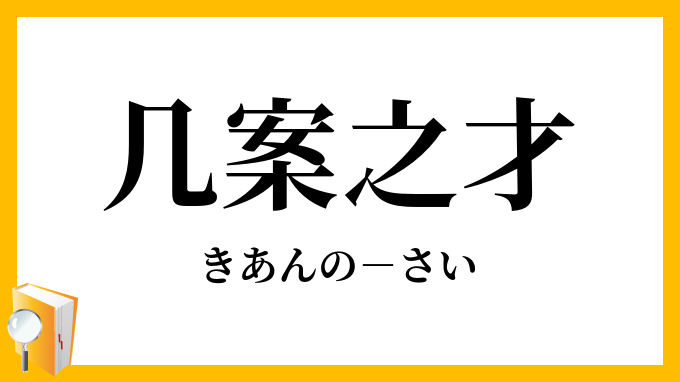
| 四字熟語 | 几案之才 |
|---|---|
| 読み方 | きあんのさい |
| 意味 | 美しい文章を作る才能のこと。 または、その才能を持っている人のこと。 「几」と「案」はどちらも机のこと。 「机案之才」とも書く。 |
| 出典 | 『魏書』「李遐伝」 |
| 異形 | 机案之才(きあんのさい) |
| 場面用途 | 才能がある |
| 使用語彙 | 才 |
| 使用漢字 | 几 / 案 / 之 / 才 / 机 |
「几」を含む四字熟語
- 几案之才(きあんのさい)
- 几杖不朝(きじょうふちょう)
- 明窓浄几(めいそうじょうき)
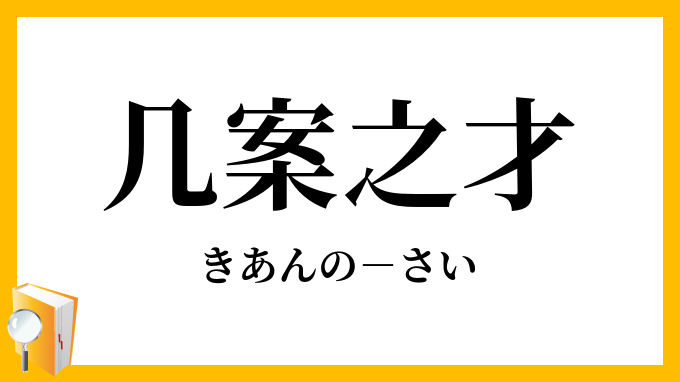
| 四字熟語 | 几案之才 |
|---|---|
| 読み方 | きあんのさい |
| 意味 | 美しい文章を作る才能のこと。 または、その才能を持っている人のこと。 「几」と「案」はどちらも机のこと。 「机案之才」とも書く。 |
| 出典 | 『魏書』「李遐伝」 |
| 異形 | 机案之才(きあんのさい) |
| 場面用途 | 才能がある |
| 使用語彙 | 才 |
| 使用漢字 | 几 / 案 / 之 / 才 / 机 |