蓴羹鱸膾とは
蓴羹鱸膾
じゅんこう-ろかい
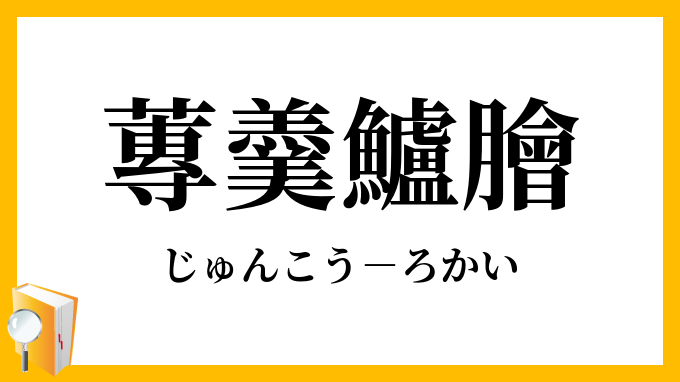
| 四字熟語 | 蓴羹鱸膾 |
|---|---|
| 読み方 | じゅんこうろかい |
| 意味 | 故郷のことを懐かしいと思う気持ちのこと。
または、故郷の懐かしい味のこと。 「蓴羹」はじゅんさいの吸い物。 「鱸膾」は魚のすずきのなます。 中国の晋の張翰は、故郷の食事であるじゅんさいの吸い物と、すずきのなますが恋しくなり、官職を辞めて洛陽から帰郷したという故事から。 |
| 出典 | 『晋書』「張翰伝」 |
| 漢検級 | 1級 |
| 場面用途 | 故郷を懐かしむ / 故郷 |
| 類義語 | 越鳥南枝(えっちょうなんし) |
| 狐死首丘(こししゅきゅう) | |
| 胡馬北風(こばほくふう) | |
| 池魚故淵(ちぎょこえん) | |
| 使用漢字 | 蓴 / 羹 / 鱸 / 膾 |
「蓴」を含む四字熟語
- 蓴羹鱸膾(じゅんこうろかい)
「羹」を含む四字熟語
「鱸」を含む四字熟語
- 蓴羹鱸膾(じゅんこうろかい)
「膾」を含む四字熟語
- 蓴羹鱸膾(じゅんこうろかい)
- 人口膾炙(じんこうかいしゃ)
- 懲羹吹膾(ちょうこうすいかい)



