諸行無常とは
諸行無常
しょぎょう-むじょう
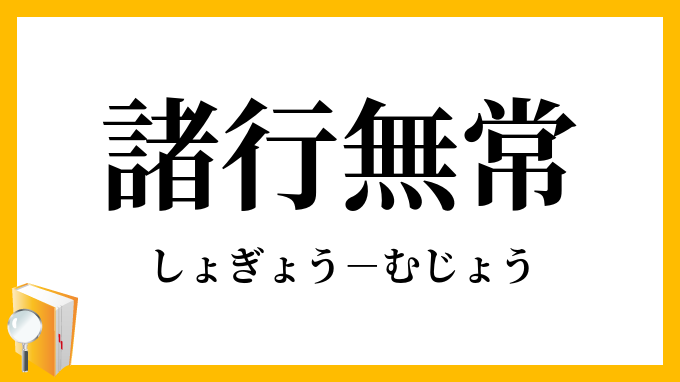
| 四字熟語 | 諸行無常 |
|---|---|
| 読み方 | しょぎょうむじょう |
| 意味 | 世の中は常に変化しており、いつまでも変化しないものや永久に無くならないものはないということ。 人生、人の命の儚さをいう言葉。 「諸行」はこの世にある全てのもの、全ての現象のこと。 「無常」は変化しないものはないという意味。 「諸行無常、諸法無我、涅槃寂静」という仏教の思想の特徴を表す三法印の一つ。 平家物語の冒頭として有名。 |
| 出典 | 『北本涅槃経』「一四」 |
| 漢検級 | 5級 |
| 場面用途 | 世の儚さ / 人生の儚さ / 変化し続ける / ことわざ |
| 使用語彙 | 諸行 |
| 使用漢字 | 諸 / 行 / 無 / 常 |



