出類抜萃とは
出類抜萃
しゅつるい-ばっすい
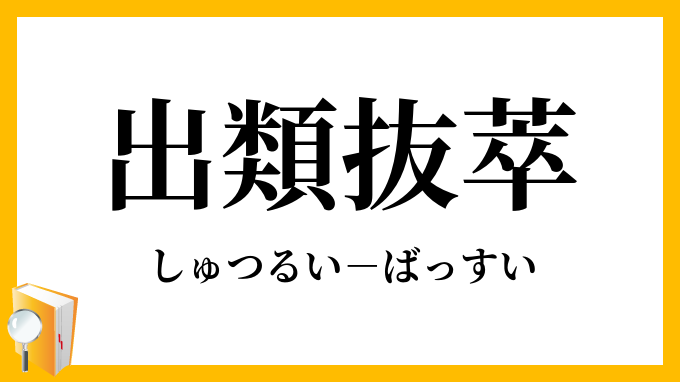
| 四字熟語 | 出類抜萃 |
|---|---|
| 読み方 | しゅつるいばっすい |
| 意味 | 同じ仲間の中のすぐれたものの中でも、さらに一際すぐれていること。
「出類」は同じ種類の中で、すぐれている人を選ぶこと。 「抜萃」はすぐれたものの中から、一際すぐれているものを選ぶということ。 「類より出(い)でて萃(すい)に抜く」とも読む。 |
| 出典 | 『孟子』「公孫丑・上」 |
| 類義語 | 抜群出類(ばつぐんしゅつるい) |
| 使用語彙 | 抜萃 |
| 使用漢字 | 出 / 類 / 抜 / 萃 |
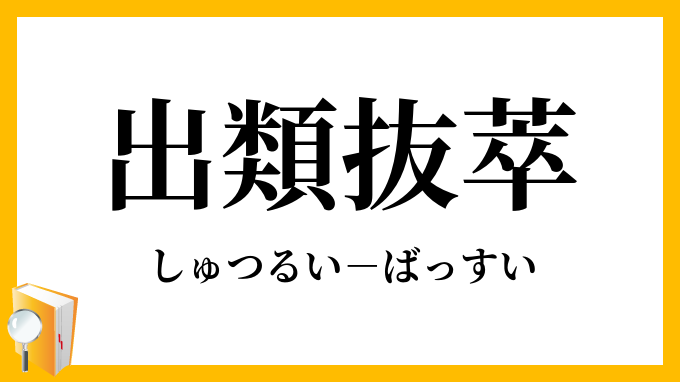
| 四字熟語 | 出類抜萃 |
|---|---|
| 読み方 | しゅつるいばっすい |
| 意味 | 同じ仲間の中のすぐれたものの中でも、さらに一際すぐれていること。
「出類」は同じ種類の中で、すぐれている人を選ぶこと。 「抜萃」はすぐれたものの中から、一際すぐれているものを選ぶということ。 「類より出(い)でて萃(すい)に抜く」とも読む。 |
| 出典 | 『孟子』「公孫丑・上」 |
| 類義語 | 抜群出類(ばつぐんしゅつるい) |
| 使用語彙 | 抜萃 |
| 使用漢字 | 出 / 類 / 抜 / 萃 |