君子豹変とは
君子豹変
くんし-ひょうへん
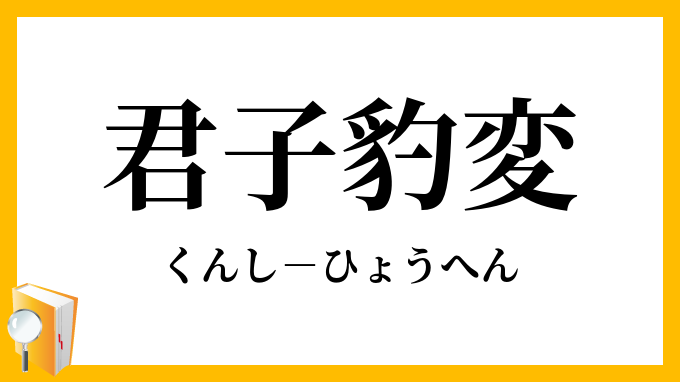
| 四字熟語 | 君子豹変 |
|---|---|
| 読み方 | くんしひょうへん |
| 意味 | 信念を持たずに考えや態度をあっさりと変えること。 元は「人格者は間違いをすぐに認めて改める」という良い意味で使われていたが、現在は悪い意味で使われることが多い言葉。 「君子」は徳のあるすばらしい人物のこと。 「豹変」は豹の毛が生え変わるときに模様が美しく変化することで、ここでは考えや態度を急に変えることのたとえ。 |
| 出典 | 『易経』「革卦」 |
| 漢検級 | 準1級 |
| 場面用途 | 反省 / 考える / ことわざ |
| 類義語 | 大賢虎変(たいけんこへん) |
| 大人虎変(たいじんこへん) | |
| 使用語彙 | 君子 |
| 使用漢字 | 君 / 子 / 豹 / 変 |



