優勝劣敗とは
優勝劣敗
ゆうしょう-れっぱい
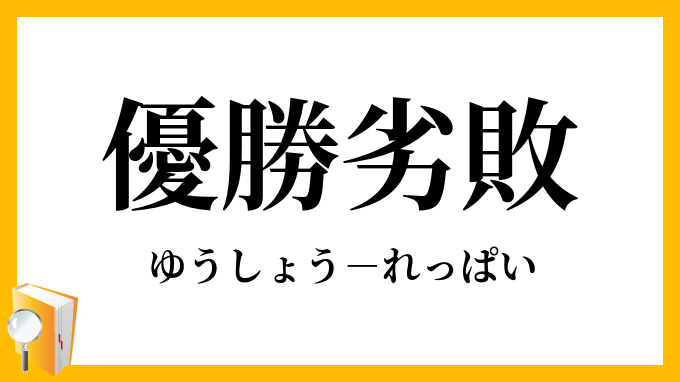
| 四字熟語 | 優勝劣敗 |
|---|---|
| 読み方 | ゆうしょうれっぱい |
| 意味 | 能力のある者が勝ち、劣っている者が負けること。 生存競争で強者が繁栄して、弱者が滅亡すること。 |
| 漢検級 | 4級 |
| 類義語 | 自然淘汰(しぜんとうた) |
| 弱肉強食(じゃくにくきょうしょく) | |
| 適者生存(てきしゃせいぞん) | |
| 使用語彙 | 優勝 |
| 使用漢字 | 優 / 勝 / 劣 / 敗 |
「優」を含む四字熟語
「勝」を含む四字熟語
「劣」を含む四字熟語
- 浅薄愚劣(せんぱくぐれつ)
- 土豪劣紳(どごうれっしん)
- 優勝劣敗(ゆうしょうれっぱい)



