窃鈇之疑とは
窃鈇之疑
せっぷの-ぎ
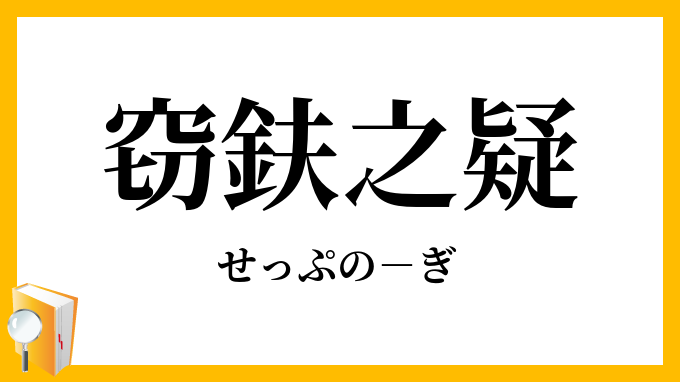
| 四字熟語 | 窃鈇之疑 |
|---|---|
| 読み方 | せっぷのぎ |
| 意味 | 証拠もないのに疑うこと。また、疑う気持ちを持って見ていると、その人の言動が全て怪しく見えることのたとえ。
「鈇」は斧のこと。 斧を盗まれたと思った男性が隣人の女性を疑うと、その女性の立ち居振る舞いの全てが疑わしく思えたが、斧が物置で見つかるとその女性の全てがかわいらしく思えたという故事から。 「せっぷのうたがい」とも読む。 |
| 出典 | 『列子』「説符」 |
| 漢検級 | 準1級 |
| 類義語 | 疑心暗鬼(ぎしんあんき) |
| 使用漢字 | 窃 / 鈇 / 之 / 疑 |



