版籍奉還とは
版籍奉還
はんせき-ほうかん
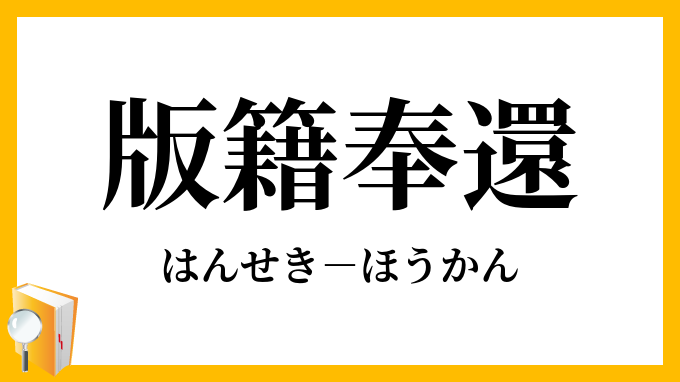
| 四字熟語 | 版籍奉還 |
|---|---|
| 読み方 | はんせきほうかん |
| 意味 | 明治維新の後に行われた政治改革で、日本全国の藩主が朝廷に領地と領民を返還したこと。 「版籍」は版図と戸籍のことで、土地と領民のこと。 「奉還」は返すという意味の言葉で、それを謙って言う言葉。 「藩籍奉還」とも書く。 |
| 異形 | 藩籍奉還(はんせきほうかん) |
| 漢検級 | 準2級 |
| 場面用途 | 政治 |
| 使用漢字 | 版 / 籍 / 奉 / 還 / 藩 |
「版」を含む四字熟語
- 版籍奉還(はんせきほうかん)
「籍」を含む四字熟語
- 阮籍青眼(げんせきせいがん)
- 載籍浩瀚(さいせきこうかん)
- 版籍奉還(はんせきほうかん)
- 名声籍甚(めいせいせきじん)



