虚静恬淡とは
虚静恬淡
きょせい-てんたん
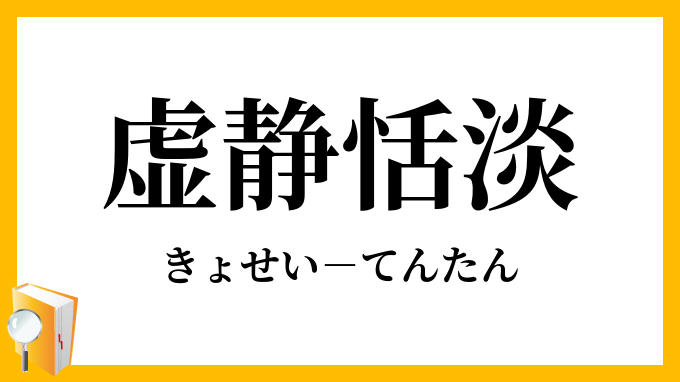
| 四字熟語 | 虚静恬淡 |
|---|---|
| 読み方 | きょせいてんたん |
| 意味 | 私心や私欲が全くなく、心が落ち着いていていること。 「虚静」は心の中に不信や疑念などがなく、落ち着いていること。 「恬淡」は私欲がなく、あっさりとしていること。 「虚静恬澹」とも、「虚静恬憺」とも書く。 |
| 出典 | 『荘子』「天道」 |
| 異形 | 虚静恬澹(きょせいてんたん) |
| 虚静恬憺(きょせいてんたん) | |
| 漢検級 | 1級 |
| 場面用途 | 平静 / 清廉 / 無欲 / 性質 / 状態 |
| 類義語 | 雲烟過眼(うんえんかがん) |
| 虚無恬淡(きょむてんたん) | |
| 無欲恬淡(むよくてんたん) | |
| 使用漢字 | 虚 / 静 / 恬 / 淡 / 澹 / 憺 |



