紫電一閃とは
紫電一閃
しでん-いっせん
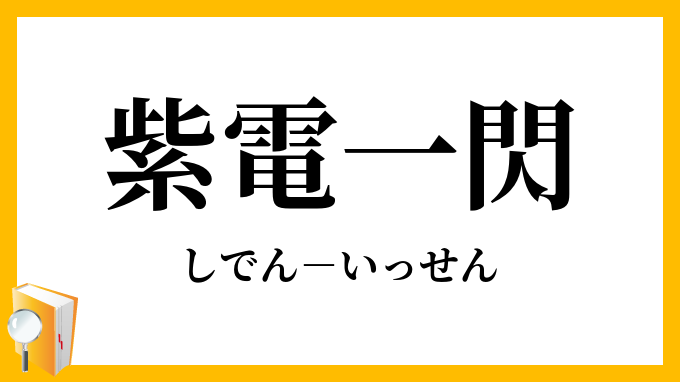
| 四字熟語 | 紫電一閃 |
|---|---|
| 読み方 | しでんいっせん |
| 意味 | 刀剣を振り下ろす瞬間に稲妻のようにきらめく様子。転じて、事態が切迫していること。極めて短い時間で急激に変化すること。
「紫電」は刀の振りによって生じる瞬間的な光、「一閃」は一瞬のひらめき。 |
| 漢検級 | 準1級 |
| 場面用途 | 時間 / 瞬間 / 激動 / 時世 |
| 類義語 | 光芒一閃(こうぼういっせん) |
| 疾風迅雷(しっぷうじんらい) | |
| 電光石火(でんこうせっか) | |
| 使用語彙 | 紫電 / 一閃 |
| 使用漢字 | 紫 / 電 / 一 / 閃 |
「紫」を含む四字熟語
「電」を含む四字熟語
「一」を含む四字熟語
「閃」を含む四字熟語
- 光芒一閃(こうぼういっせん)
- 紫電一閃(しでんいっせん)
- 霹靂閃電(へきれきせんでん)



