拒諫飾非とは
拒諫飾非
きょかん-しょくひ
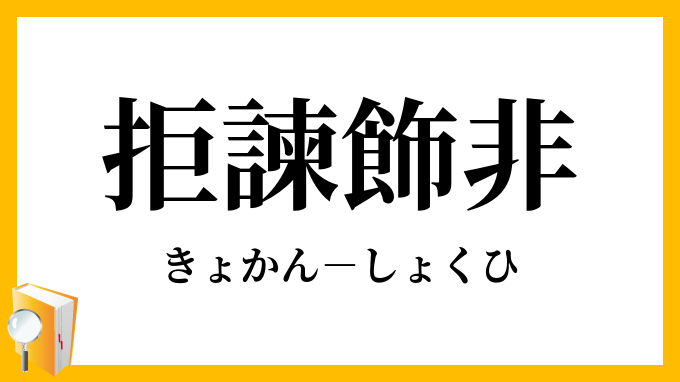
| 四字熟語 | 拒諫飾非 |
|---|---|
| 読み方 | きょかんしょくひ |
| 意味 | 他人からの忠告を聞かず、道理にそむいた行いの言い訳をすること。
「拒諫」は他人からの忠告を受け入れないこと。 「飾非」は道理にそむいた行いの言い訳をすること。 「諫(かん)を拒(こば)み非を飾る」とも読む。 |
| 出典 | 『荀子』「成相」 |
| 場面用途 | 屁理屈をこねる |
| 使用漢字 | 拒 / 諫 / 飾 / 非 |
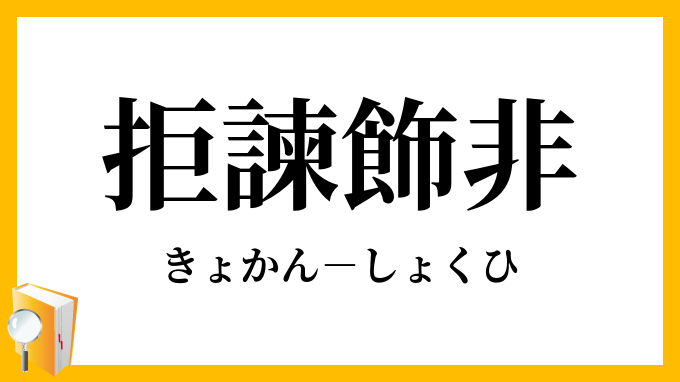
| 四字熟語 | 拒諫飾非 |
|---|---|
| 読み方 | きょかんしょくひ |
| 意味 | 他人からの忠告を聞かず、道理にそむいた行いの言い訳をすること。
「拒諫」は他人からの忠告を受け入れないこと。 「飾非」は道理にそむいた行いの言い訳をすること。 「諫(かん)を拒(こば)み非を飾る」とも読む。 |
| 出典 | 『荀子』「成相」 |
| 場面用途 | 屁理屈をこねる |
| 使用漢字 | 拒 / 諫 / 飾 / 非 |