濠濮間想とは
濠濮間想
ごうぼくかんの-おもい
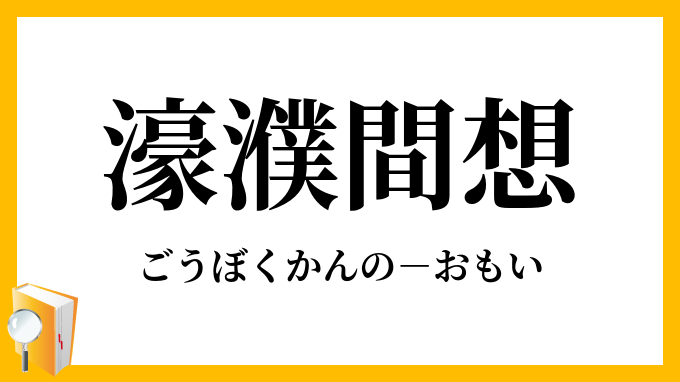
| 四字熟語 | 濠濮間想 |
|---|---|
| 読み方 | ごうぼくかんのおもい(ごうぼくのかんそう) |
| 意味 | 世間から離れて、自然の中で静かに楽しむ心のこと。 「濠」は濠水、「濮」は濮水のことで、どちらも中国の川の名前。 中国の戦国時代の荘子は、楚王からの丞相にするという招きを断り、濠水で魚が遊ぶのを見て楽しみ、濮水で魚を釣って楽しんだという故事から。 |
| 出典 | 『世説新語』「言語」 |
| 場面用途 | 隠居 / 礼儀 / 生活 |
| 類義語 | 濠梁之上(ごうりょうのうえ) |
| 濠梁之想(ごうりょうのおもい) | |
| 使用漢字 | 濠 / 濮 / 間 / 想 |
「濠」を含む四字熟語
- 濠濮間想(ごうぼくかんのおもい)
「濮」を含む四字熟語
- 濠濮間想(ごうぼくかんのおもい)
- 桑間濮上(そうかんぼくじょう)



