左戚右賢とは
左戚右賢
させき-ゆうけん
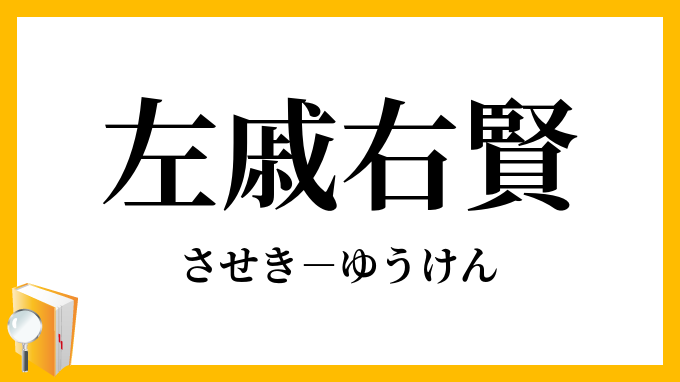
| 四字熟語 | 左戚右賢 |
|---|---|
| 読み方 | させきゆうけん |
| 意味 | 親族を低い地位の左側に、賢者を高い地位の右側に置くこと。
卑しいものを左側、尊ぶものを右側に置く中国の漢の時代の風習。 「右賢左戚」ともいう。 |
| 出典 | 『漢書』「文帝紀」 |
| 異形 | 右賢左戚(ゆうけんさせき) |
| 漢検級 | 2級 |
| 使用漢字 | 左 / 戚 / 右 / 賢 |
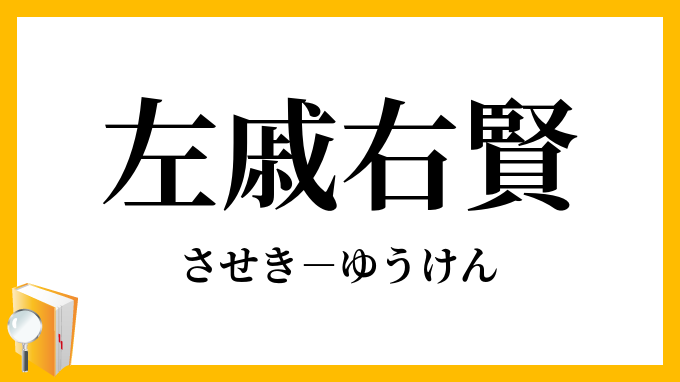
| 四字熟語 | 左戚右賢 |
|---|---|
| 読み方 | させきゆうけん |
| 意味 | 親族を低い地位の左側に、賢者を高い地位の右側に置くこと。
卑しいものを左側、尊ぶものを右側に置く中国の漢の時代の風習。 「右賢左戚」ともいう。 |
| 出典 | 『漢書』「文帝紀」 |
| 異形 | 右賢左戚(ゆうけんさせき) |
| 漢検級 | 2級 |
| 使用漢字 | 左 / 戚 / 右 / 賢 |