多士済済とは
多士済済
たし-せいせい
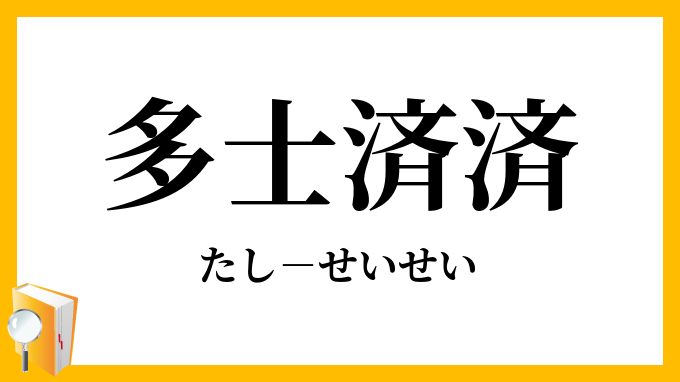
| 四字熟語 | 多士済済 |
|---|---|
| 読み方 | たしせいせい(たしさいさい) |
| 意味 | 優れた能力や才能のある人物がたくさんいること。また、その様子。
「多士」は優れた才能や能力を持っている多くの人たちのこと。 「済済」は数が多くて盛んな様子や、立ち振る舞いの礼儀作法が整っていて立派なこと。 「済」を「さい」と読むことは本来は誤用。 「済済多士」ともいう。 |
| 出典 | 『詩経』「大雅・文王」 |
| 異形 | 多士済々(たしせいせい) |
| 済済多士(せいせいたし) | |
| 済々多士(せいせいたし) | |
| 漢検級 | 準1級 |
| 類義語 | 人才済済(じんさいせいせい) |
| 使用語彙 | 多士 |
| 使用漢字 | 多 / 士 / 済 / 々 |



