剣抜弩張とは
剣抜弩張
けんばつ-どちょう
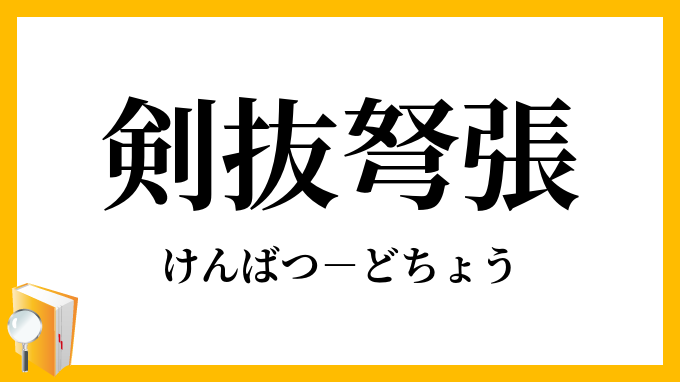
| 四字熟語 | 剣抜弩張 |
|---|---|
| 読み方 | けんばつどちょう |
| 意味 | 戦闘が始まる直前のような緊張した状況のこと。
または、書道で筆勢に激しい気迫がこもっていることのたとえ。 剣を鞘(さや)から抜いて、石弓に矢をつがえて弦を引くことから。 「弩」は矢や石を飛ばすことのできる機械、石弓。 「張」は弦を引いて張ること。 「弩張剣抜」ともいう。 |
| 出典 | 『漢書』「王莽伝・下」 |
| 異形 | 弩張剣抜(どちょうけんばつ) |
| 漢検級 | 1級 |
| 場面用途 | 緊迫 |
| 類義語 | 一触即発(いっしょくそくはつ) |
| 刀光剣影(とうこうけんえい) | |
| 使用漢字 | 剣 / 抜 / 弩 / 張 |



