被髪佯狂とは
被髪佯狂
ひはつ-ようきょう
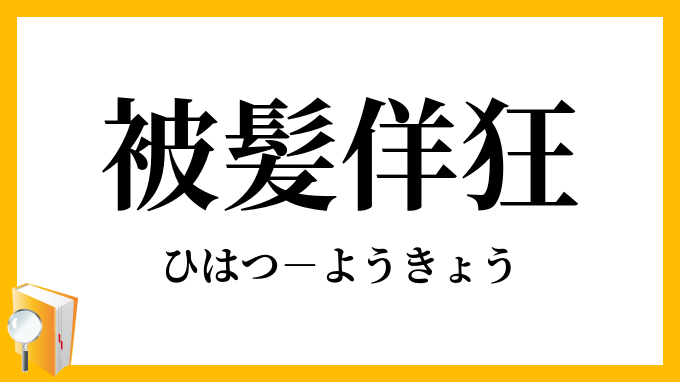
| 四字熟語 | 被髪佯狂 |
|---|---|
| 読み方 | ひはつようきょう |
| 意味 | 髪を振り乱して、気がふれた人のふりをすること。
「被髪」は束ねずに乱れた髪の毛。 「佯狂」は狂っているかのように見せかけること。 古代中国の殷の紂王の臣下である箕子は、暴政を行う紂王を諫(いさ)めたが聞き入れられなかった。 君主のもとを去れば、君主の悪が公になってしまい、また、自分自身を弁解することにもなってしまうと考えた箕子は、髪を乱し、狂ったふりをして奴隷となったという故事から。 |
| 出典 | 『史記』「宋世家」 |
| 漢検級 | 1級 |
| 使用語彙 | 佯狂 |
| 使用漢字 | 被 / 髪 / 佯 / 狂 |



